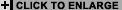|
TOPページ > ハービー・山口の「雲の上はいつも青空」 >第93話 『それぞれの誠実』 
第93話 『それぞれの誠実』
2013年公開の映画「東京シャッターガール」に高校の写真部の顧問役で出演させて頂いた時、実際の撮影のロケに使ったのがJR中野駅のすぐそばにある廃校だった。それは2013年の6月のことだった。まだ真夏には間がある、でもあたりの空気はちょっと蒸し暑く、良く晴れた日だった。学校の周囲の小径は住宅街で、まだきれいな緑の雑草が、時折吹く風に揺れていた。撮影に使われる教室の隣の部屋が我々出演者の控え部屋になっていて、僕がその部屋に入って行った時には高校生役の俳優さんたちが一足早く来ていて、緊張感というより、どこかまったりとした雰囲気を作っていた。僕は何年もご無沙汰していた演技に向けて少々の緊張感はあったが、彼らとのコミュニケーションが大切だと思い、「実は僕は本当は写真家でね、でも昔は役者の経験が少しあって、、」と積極的に彼らに話しかけていた。「えー、そうなんですか!!」特に白いセーラー服を着た女の子たちが反応してくれて、そんな彼女たちに向かって、数枚のシャッターを切って交流を図ろうとしていたのである。 お陰で撮影は上手くいき、ワンテイクで長い台詞をこなすことが出来た。特にアラーキーさんの写真集について語る場面で、「天国から奥さんがこの写真を撮ってと、頼んだんじゃないかと思うんだ、、」という台詞では、自分でも予期しなかった感情が沸き起こり、思わず涙声になってしまうのを、ぎりぎりでこらえて演技していた。僕を取り囲んだ写真部の女子も男子も、僕の言葉を身に染み込ませる様に静かに聴いている様が良く伝わってきたのだった。 さて、それから一ヶ月後の7月7日である。僕は宮城県石巻にいた。もうかなり真夏になっていて、強い太陽が地平を照らしていた。この地の高校を会場にして、近隣の高校から参加した写真部員およそ20名が参加するワークショップが開かれようとしていた。僕が講師となり、チャリティーカレンダーを作ろうというのだ。大伸社は広告やポスターのデザインなどを業務とする会社であるが東北の復興を願い、毎年形を変えてチャリティーカレンダーを作っている。僕は以前にも大伸社からお声をかけて頂き一昨年のチャリティーカレンダーに参加させて頂いた。そして2013年は新たな趣向として、石巻で僕が講師のワークショップ開き、皆の写真を構成してカレンダーを作ろうということになった。 夏休み最中のイベントであるが、7校から20数名の生徒たちが元気よく参加してくれた。恐らく家でゴロゴロとしていたいだろうに、暑さをものともせず参加した生徒は、参加しようとする心意気だけでも素晴らしい。参加して良かった、と一生の思い出になる位のワークショップになる様に頑張ろうと強く思ったのである。ワークショップの中身は、僕の写真観、希望を撮りたいと思うに至った僕の歴史、写真を通しての夢を語るトーク、実際に廊下や体育館、校庭などでの撮影実習、そしてプリントアウトして講評をするなどだ。 始めは固かった高校生たちだったが、あだなを付けて呼ぶ様にすると、徐々にほぐれてきた。特に一人二人おとなしい男子がいたので、あえて彼らに、マーティンとかジョンという名前で呼び始めると、まんざらではないようで、このワークショップの空気が出来上がって来た。午後の撮影では、体育館でバスケットボール部を撮り、校庭では草原に寝転んだマーティンが女子からカメラを向けられていた。その得意で嬉しそうな表情は午前中のふさぎ込んでいた彼とは全く違う彼の心の内を物語っていた。撮影実習の最後に、全員に校庭で一列になってもらい、僕のライカM モノクロームというモノクロしか撮れないデジタルカメラで、彼らを撮った。僕は草の上に這いつくばってローアングルで撮った。雑草や黄色い小さな花が画面の前景になり、すると雑草越しに彼らを見ていることになった。草花はかすかな自然の匂いを放ち、全員の頭上に拡がる青空とを合わせ見ると、何か懐かしさがこみ上げて来た。人々と大自然とがハーモニーを作る一瞬だ。それは人間の存在の原点なのだろうか。一列に並ぶ高校生の男女に夏の光りがまとわりついて、なお一層、僕が子供の頃の夏休みを連想させた。 しばらくして僕たちは教室に入り、講評会を始めた。2〜3名の印象に残った写真にハービー賞として、サイン入りポストカードを贈った。夕方頃無事全ての行程が終了した。 それからおよそ一ヶ月が過ぎた。参加した一人、Aさんからメールが届いた。「やはり、私の写真家になる決意は固くて、ハービーさんが使っていたライカのモノクロームを注文したんです。」 確かに写真はカメラを使わないと撮れない。そのカメラと写真家とはある種の共感でつながりあっている。カメラは何だっていいんです、という方も沢山いるけれど、僕はカメラから撮る勇気をもらってきたタイプだ。 「どんな写真を撮りたいと思う?」 「先日、自分が写った家族のアルバムを見ていて思ったんですけど、この写真は全て、私の両親が100パーセントの愛情を持って私たちを撮ってくれた写真なんです。その100パーセントの愛情を持って街の人たちを撮ってみたいんです。」 Aさんとのメールのやりとりから2ヶ月が経った。東京、ライカ銀座店では、ロバートキャパの生誕100年を記念して写真展が企画され、そのオープニングレセプションが開かれた。その日はロバートキャパの誕生日にあたった。大勢の人々と挨拶をする中で、ライカのオーナー、アンドレアス・カウフマン氏と再会した。2年ほど前に来日された折にライカカメラジャパンの方から紹介されたのが初対面だった。氏は前回のことを憶えていただいていて、「以前会いましたよね、」と微笑んで下さった。その笑顔が何とも人の心を開かせる力を持っていた。 レセプションの後、お食事ご一緒にいかがですか、とお誘いを受けた。僕がご一緒して良いものか、一瞬ためらったが、ライカカメラジャパンの方のお言葉に甘えた。地下にあるフレンチレストランだった。カウフマン氏が中央の席に着かれた。すると、ライカカメラジャパンの福家社長が、「ハービーさん、カウフマンさんのお隣の席にどうぞ」とおっしゃった。さすがにそれは出来ない。「いえ、それはいくら何でも、、。」固持する僕であったが、福家社長は「どうぞ、どうぞ」と仰り、僕はカウフマン氏のお隣に着席させて頂いたのである。 話を急ごう。あるタイミングで僕はカウフマン氏に自分の写真、カメラ論を話し始めたのである。赤ワインのかすかな酔いが僕を勢いづかせたのかも知れない。 「世界の写真家が撮った写真に込められたメッセージは、やがて大きなうねりとなって、世界を平和な方向へ変えて行くのだと思うんです。ですから、カメラは世界一平和な道具だと思っています!」 氏は僕の方に体を少し傾け、僕の言葉を無言で聞かれていた。すると氏の表情が一変したのだ。どこか、それまでの笑顔とは違いシリアスというのだろうか、立場とか階級とかを越えた人間の素に戻った様な表情だった。 そして、僕はふと頭をよぎった、石巻のワークショップに参加しライカを買うというAさんの話をした。若い世代の人間が、写真にどんな情熱を持っていて、カメラとどう関わっているのかの一例だと思ったからだ。 Aさんとは電話やメールで連絡をとった。カウフマン氏のことを伝えると、勿論卒倒してしまうくらいに驚いていた。 翌年、2014年3月、ライカ京都店のオープニングに出席のため、再び来日されたカウフマン氏は、その2日前、ライカ銀座店を訪れた。その日、まだ寒さが残っている、でも良く晴れた午後、Aさんにカメラ一式を氏個人からとして贈呈したのだった。氏はいつもの笑顔を浮かべ、Aさんの胸にかかったライカMモノクロームとズミクロン35ミリを満足そうに眺めていた。 5月、僕は早春のドイツ、ウエッツラーにいた。初めて訪れるライカ誕生の聖地である。ウル・ライカが作られてから丁度今年が100年となる。その記念すべき年にライツパークという立派な建物が完成した。世界から2000名のライカの関係者がこのビルのオープニングに出席した。それはカメラの製作会社のイベントというには余りにも上流で、文化の香りがした。この街には、1700年代に建てられた独特の木組みの家が、細い石畳の坂道に絡む様に建てられ、時間と共に傾いても、建物同士が支え合って歴史や景観を守っているようだ。それはパステルカラーの水彩画に描かれたおとぎの国の街並を見ている様な、少し曲がっていて、色とりどりで、心奪われる景観だった。寒くも暑くもない、丁度肌に優しいそよ風が、細い坂道を吹き抜けていた。そして時折、路地の先を見渡すと、白く角張った旧社屋の屋上に設置されたLEITSの赤いマークが目に止まるのだった。その中心街から、少し郊外に行った、一面の緑の畑が見渡せる高台にライツパークはあった。双眼鏡とレンズの鏡胴をモティーフにしたという曲線を全ての壁面にも持ち、堂々と誇らしげに建っていた。 翌日、オープニングを記念してのプレス会見があった。建物の隣の空き地に作られた巨大な黒いテントがその会場である。ほとんどの参加者が黒いスーツをまとい、ライカM9やM・Eなども携えている光景は正に圧巻であった。その中にエリオット・アーウィット氏が登場したりと、ヨーロッパの上流階級の社交場を思わせる光景であった。 「ライカはこれまで優れたカメラを作って来たのだから、これからもさらなるカメラを作り続けていきたい。そして忘れてはならないのが、強い写真には人の心を動かす力が備わっているということだ。カメラによって撮られた写真が持つメッセージを良いカメラを作るのと同等に大切なものと考え、写真展示のギャラリーの充実をはかって行きたいと思う。」 そしてギャラリーを担当するカリン・カウフマン氏は「先人たちが残してくれた写真の伝統を継続していくことと、これから生まれてくる現代写真を取り上げることにより、伝統と未来の架け橋となることを目標としたい。」 後半に宿泊したホテルにはエリオット・アーウィットさんも泊まっていて、ほぼ毎日ロビーで顔を合わせ短い会話と握手を交わせたのである。そしてある日の午前、ロビーで紅茶を飲んでいるとジュセフ・クーデルカさんが偶然入って来て、僕を見つけると満面の笑みを浮かべ両手を水平に大きく拡げた。若葉と射し込む日の光が彼を包んでいた。僕はズミクロン50ミリの付いたM6で彼に向かって3回シャッターを切り、直後彼は僕をがっちりと抱き込んだのだった。 彼はポケットから黄色い地の出たM4ブラックペイントに35ミリ6枚玉付きを取り出し、こちらにレンズを向けたのであった。 2013年 から2014年にかけての出来事。それは、僕の人生の中でも最も素晴らしい一年だった。 |